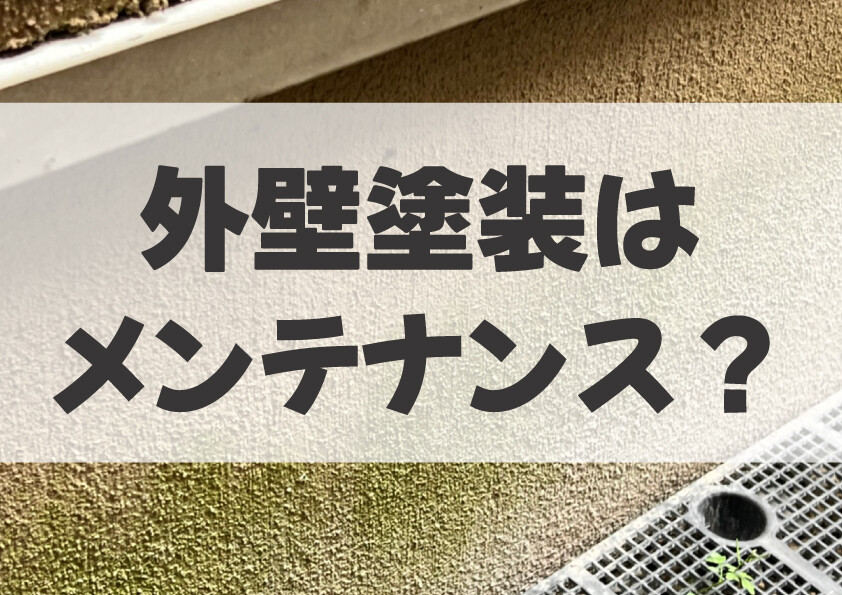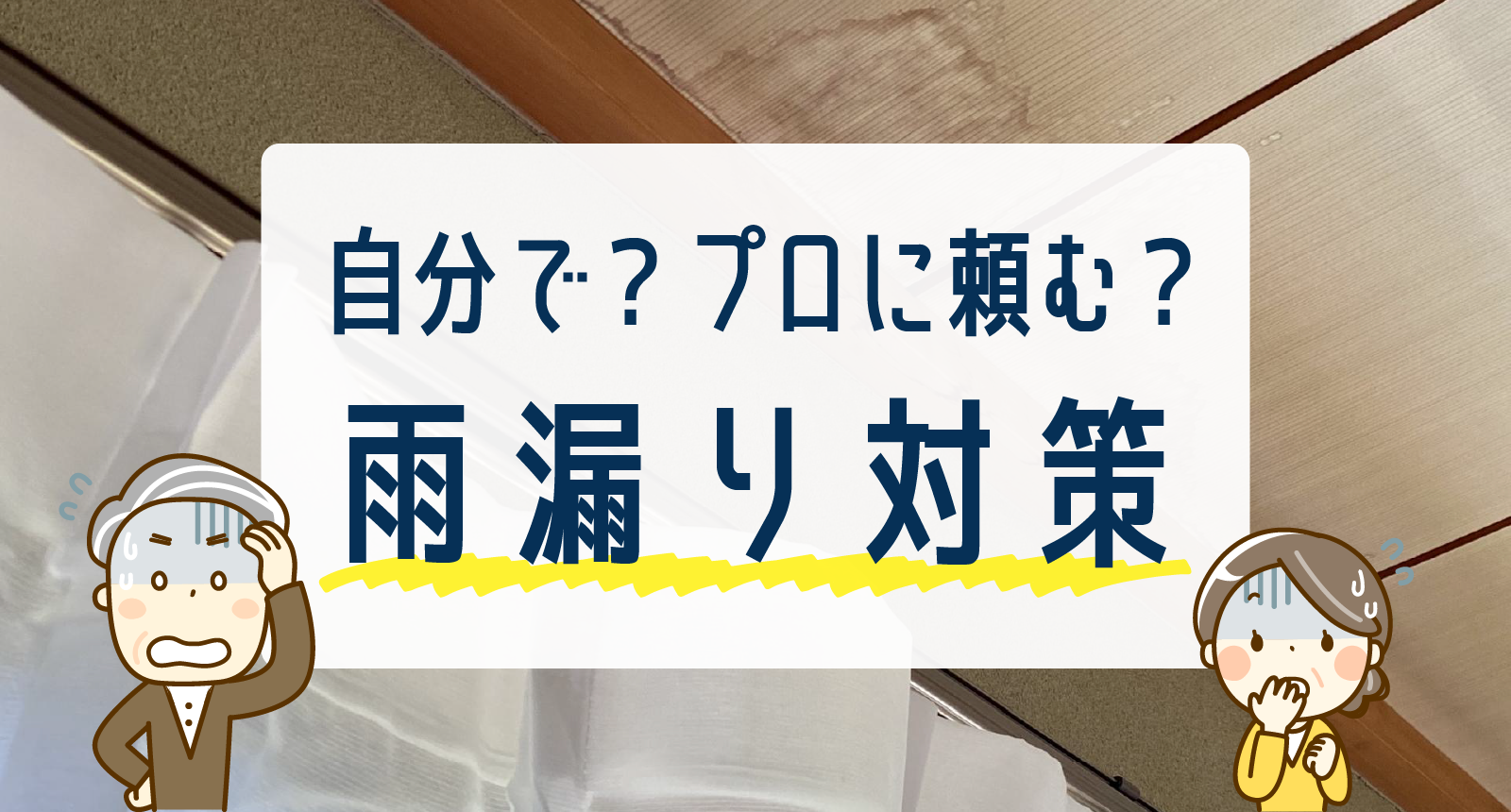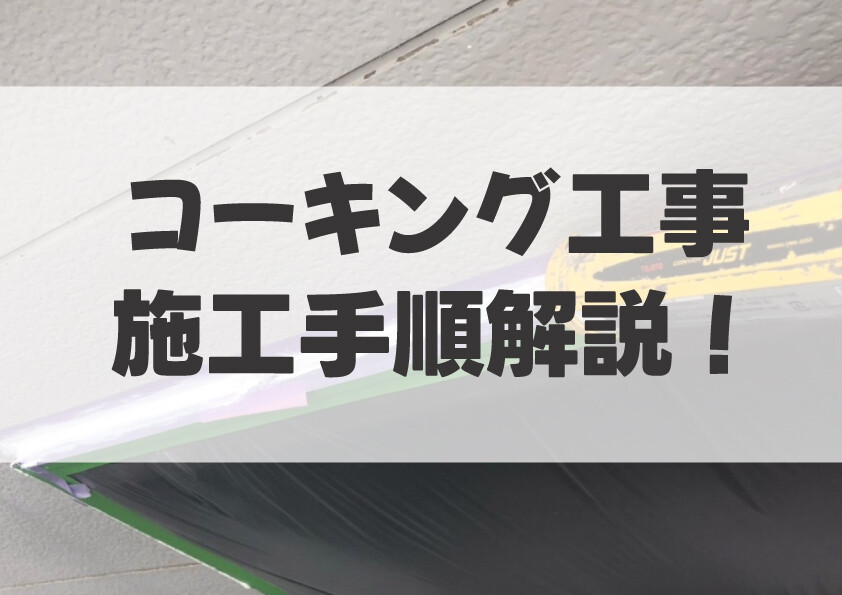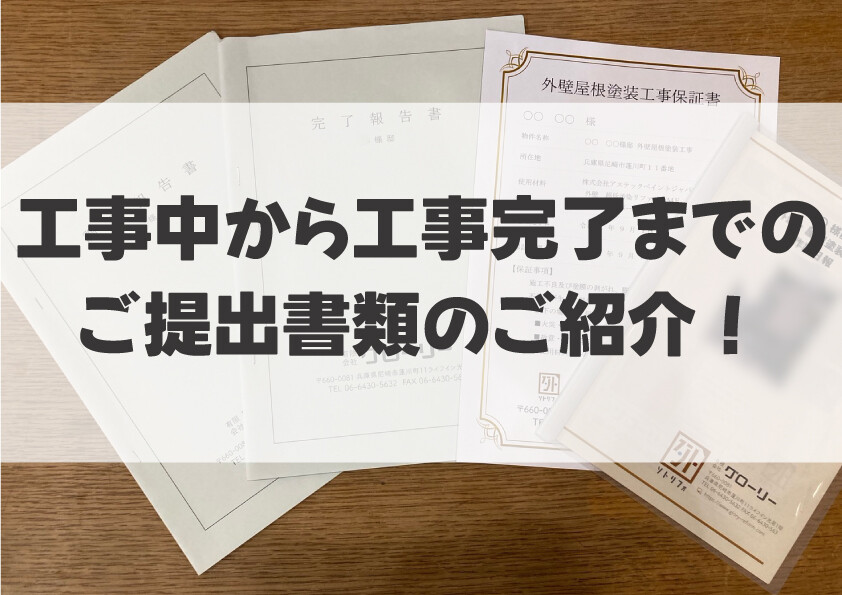【セルフチェック】瓦の種類で見分けよう!塗装が必要な屋根と不要な屋根
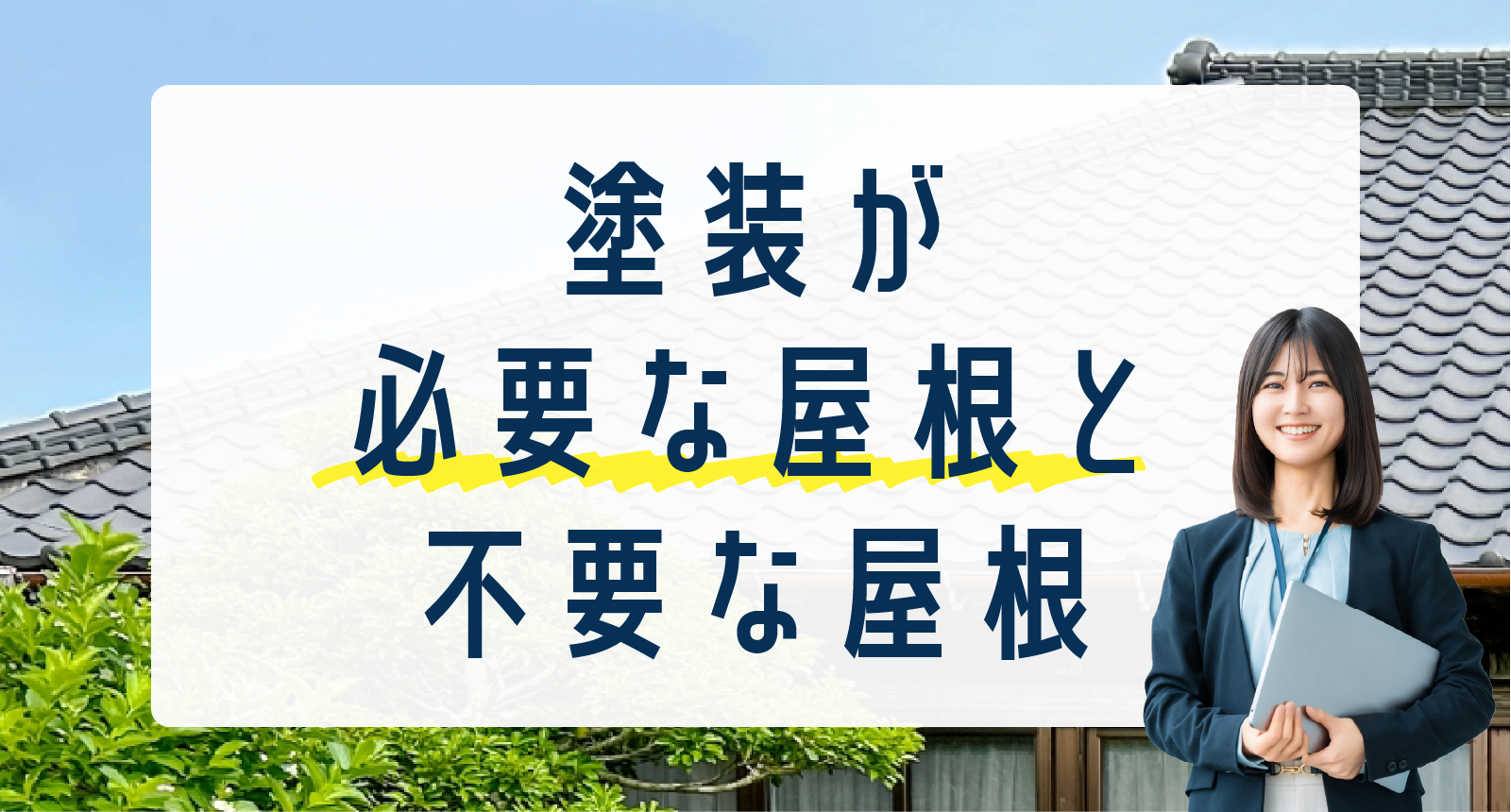
「うちの家は瓦屋根だから塗装は必要ない」と思っていませんか?
実は、瓦にはいくつかの種類があり、塗装が必要なものと不要なものがあります。
塗装が必要かどうかの判断は、プロにおまかせいただくのが大前提ではありますが、ご自身の家のこと。
予備知識として知っておきたいですよね?

この記事では、見た目の特徴や仕上げの違いから、あなたの家の瓦がどのタイプか判断できるように整理しました。
プロへのお問合せの参考になりましたら幸いです。
Step1:光沢がある→釉薬瓦(塗装不要)
表面にツヤがあり、陶器のような光沢が見える場合は「釉薬瓦」です。
釉薬(ゆうやく)とは瓦の表面を覆うガラス質の膜で、防水・防汚の役割があります。
すでに表面処理が完成しているため、塗装は不要です。
Step2:ツヤはないが銀色を帯びた渋い色→いぶし瓦(塗装不要)
黒っぽく銀色がかった落ち着いた色合いの瓦は「いぶし瓦」です。
これは最後に燻化(くんか)という処理を行って、炭素の膜をまとった仕上げになっています。
この場合、炭素の膜にすでに防護性能があるため、塗装は不要です。
Step3:ザラザラした質感、コンクリートのよう→セメント瓦(塗装が必要)

セメントを型に流して固めた瓦で、表面の塗装が防水の役割を担っています。
塗膜が劣化すると吸水や劣化が進んで強度が低下するため、定期的な塗装が必要です。
Step4:セメント瓦に似ていて模様や着色がある→モニエル瓦(基本は塗装不要)
モニエル瓦は、日本では1990年代まで流通していました。
一見セメント瓦に似ていますが、表面に「スラリー層」という特殊な層があります。
この層が防水性を持っているため、本来は塗装不要です。
スラリー層には塗料が密着しにくい性質があり、誤って塗装するとすぐに剥がれます。
塗装を考える場合はモニエル瓦の施工経験がある専門業者に必ず相談しましょう。
Step5:素焼きのオレンジ色で色あせが目立つ→無釉薬テラコッタ瓦(場合によって塗装が必要)

釉薬がかかっていないテラコッタ瓦は、焼き物として高温で焼成されているため、基本的には塗装を必要としない屋根材です。
一方で、釉薬瓦に比べると水を吸いやすく、色あせや劣化が進みやすいという弱点があります。
加えて、安易に塗装してしまうと、粘土瓦本来が持つメンテナンス性や耐久性といった利点を損なってしまう恐れがあります。
そのため塗装が行われるのは、外観を整えたい場合や汚れを防ぐ目的、あるいは荒天や経年劣化によって補修が不可欠になった場合などに限られ、専用塗料を用いた施工が選ばれるケースがほとんどです。
Step6:瓦ではなく薄い板状の屋根→スレート屋根(塗装が必要)
瓦と混同されやすいのが「スレート屋根」です。
厚さ5mm前後の薄い板状で、主にセメントに繊維を混ぜて作られています。
スレート屋根は、表面塗装によって防水性を維持しています。
塗膜が劣化すると雨水を吸い込み、ひび割れや苔の発生につながるため、10〜15年ごとの塗装メンテナンスが必要です。
(昔のスレートにはアスベストが含まれる製品もあり、リフォーム時は注意が必要です。)
屋根は塗装以外の定期メンテナンスが不可欠です
塗装が不要な瓦でも、長い年月で割れやズレ、漆喰(しっくい)の剥がれが起きます。
これを放置すると雨漏りにつながるため、定期的な点検と補修が大切です。
スレートやセメント瓦の場合も、塗装だけでなく割れや欠けの修繕が欠かせません。
家族を守る家、家を守る屋根。
今回の内容を参考に、「瓦屋根だから大丈夫」とは思わずに、一度ご自身の屋根を改めて見てみてください。

大切な家を守る屋根だからこそ、正しい知識を持った専門業者に任せることが何よりの安心につながります。
グローリーでは、お客様の屋根を丁寧に診断し、材質に合わせた最適なメンテナンス方法をご提案しています。
お見積もりやご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。